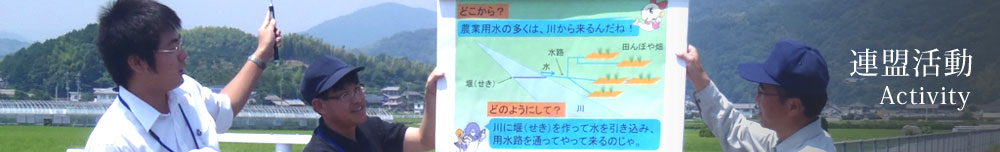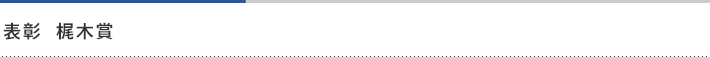第17回梶木賞受賞論文決まる!
全国農村振興技術連盟では、12月22日、(公社)土地改良測量設計技術協会 久保成隆顧問を委員長とする梶木賞審査委員会を開催し、第17回梶木賞の受賞論文が決定しました。
梶木賞は、梶木家から頂いた資金を活用し、若手技術者の資質向上を目的に、将来の農業農村整備を担う若手技術者から農村振興に関する論文を募集し、優れた論文について表彰するもので、今年度は第17回目になります。論文の募集テーマは『農業農村の直面している課題とその対応策』とし、論文内容にふさわしいタイトルをつけていただいています。
論文は、全国から30編の応募がありました。応募された論文については、12月中旬までに審査委員の一次審査により9編に絞り込み、12月22日の審査委員会において、絞り込んだ対象作品から最優秀賞1編、優秀賞2編を決定しました。
また、受賞作品は順次会誌「農村振興」に掲載する予定です。
受賞論文 講評概要
受賞論文
梶木賞の審査については、若手技術者の資質の向上を図るという梶木賞の趣旨に沿い、次の6項目の基準により審査されました。
審査基準
(1) これからの農業農村整備を担う若手技術者の、農村振興の将来に対する抱負・提言であるかどうか。
(2) 経験よりも独創性を重視。
(3) 表現が容易(わかり易く)で、説得力があるかどうか。
(4) 現地(現場)への適応性が高く、会員に周知したい内容かどうか。
(5) 農業農村整備にふさわしい内容の提言・抱負が含まれているかどうか。
(6) 普遍的なものだけではなく、ローカル的なもの、スケールの小さいものも取り上げる。
梶木賞受賞者
最優秀賞(1編)
・「農業・農村の直面している課題とその対応策」
~現場づくりから、未来の担い手を育む「ひとづくり」へ~
秋田県連盟 北野 陸
優秀賞(2編)
・「農業・農村の直面している課題とその対応策」
~農業水利施設の持続的な利用に向けて~
東北農政局連盟 吉川 日向子
・「農業・農村の直面している課題とその対応策
~農村地域の未来のためにできること~」
島根県連盟 野田 良哉