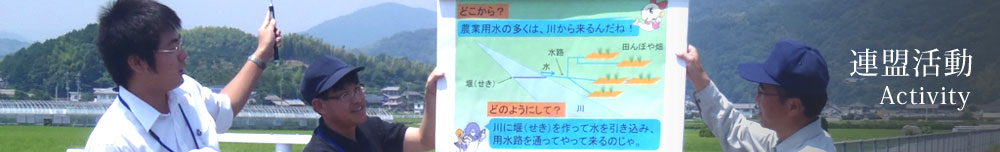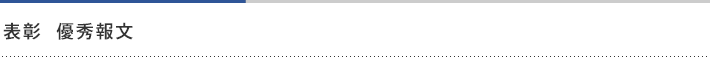令和5年「農村振興」優秀報文が決定しました!
全国農村振興技術連盟
当連盟会誌「農村振興」に掲載いたしました、令和5年1月号(第877号)から12月号(第888号)までの対象報文111編について企画幹事会(編集委員会)委員及び地方協議会選定員よる投票の結果、下表の12編を優秀報文として決定いたしました。
受賞論文 講評概要
| 掲載年.月 号 数 |
表 題 及 び 執 筆 者 | 寸 評 |
| 令和5年2月 第878号 |
【提 言】 福井県農林水産部農村振興課長 本田照男 |
近年の気候変動に伴う水害は激甚・頻発している。河川氾濫による水害を軽減するため、福井県内の各関係機関が連携して「流域治水」に取り組んでおり、農家に負担をかけず、安心して取り組めるようマニュアルを作成し、国の補助残分を県費で補助するなど、具体的な取り組みが記され、田んぼダム等の対策を進めるための参考となる。 |
| 令和5年3月 第879号 |
【農村の振興】まちからむらから 山形県農林水産部農村計画課 草 太輔 |
地域の話合いをサポートし、意思統一を図る土地改良の手法は、地域づくりに有効であるが、今後デジタル技術が進む中、人間でなければできないことが重要であり、農村部における革新を促進して、農村地域の持続的な発展を推進するための山形県の取組や人材育成がわかりやすく記されている。 |
| 令和5年3月 第879号 |
【農村の振興】まちからむらから 東広島市役所建設部用地課 専門員 大藤隆宏 |
激甚化する自然災害に対して、老朽化ため池の整備や廃止が急務となっているが、所有者不明土地の処理は全国的な課題となっており、法律改正を踏まえ、「所有者を特定することができない」土地を処理する経過や手法がわかりやすく整理されており、ため池に限らず、用地取得の具体的事例として大変参考になる取組である。 |
| 令和5年4月 第880号 |
【農村の振興】まちからむらから 福井県農林水産部農村振興課 主任 山口清一郎 |
環境配慮の取組は、計画段階のみならず、実施後も維持管理等を含め、地域に定着することが重要であり、受益者、学識経験者、地域住民との密接な調整のもと計画策定が行われており、特にビオトープについては小学生が事業内容や多面的機能などを学び、原案作りに参加していることに感銘した。 |
| 令和5年4月 第880号 |
【技術ノート】 農研機構 農村工学研究部門 小嶋 創 |
近年、豪雨や地震が頻発し大きな被害が発生している中、ため池のハザードマップ整備の重要性は大きく、その正確性が求められる。入手可能なデータによる簡易なため池ハザードマップについて、ため池決壊に伴う浸水痕跡を現地確認して、氾濫解析精度を改善する手法をわかりやすく記されており、今後の策定される浸水想定手法マニュアルへの反映が期待される。 |
| 令和5年5月 第881号 |
【海外レポート】 在オランダ日本国大使館 二等書記官 吉川 航 |
欧州やオランダにおける農業政策や農村振興政策は、地球規模で取り組むべき課題への貢献と国内産業の発展の両立がこれまで以上に求められていることをわかりやすく記しており、「今後は農業振興技術者として、持続可能性に関する知見はもちろんのこと、他分野の知見も身に着けることが必要」という部分にとても共感した。 |
| 令和5年7月 第883号 |
【農村の振興】シリーズ企画 泊環境保全協議会 代表 山内カネ子 |
地元婦人会を中心とした活動組織の設立経緯、ワークショップや環境保全活動を通じた農業者と地域住民とのコミュニティ醸成、イノシシの獣害対策、担い手となる学生たちとの連携、災害にも組織を活用するなど、わかりやすく取組が記され、離島での活発な保全活動がイメージできる報文である。 |
| 令和5年7月 第883号 |
【技術ノート】 道前平野農地整備事業所 工事第一課 池本賢弘 |
国営農地再編事業の施設は、規模は小さいが多工種にわたり、特に土を相手にする工事は検討すべき課題が多い。コンサルタントや建設会社等も交えた見学会を開催して、現場での対応を設計コンサルタントの技術者へフィードバックすることは、品質確保に加え、コスト縮減や適切な工期設定にも寄与するものであり、今後、技術者減少が進む中、技術力を確保するための取組として評価できる。 |
| 令和5年9月 第885号 |
【技術ノート】 石川農林総合事務所 主任技師 吉田敬祐 |
ほ場整備工事において、区画を大きくすると大規模な切り盛り作業となり、質が悪い下層土が出現して対策や処理に困ることが多い。予め大口径石礫の発生を想定してクッション層を計画することや、降雨後の転圧により水締効果を期待する不陸対策工法などをわかりやすく記しており、他地区でも非常に参考となる事例である。 |
| 令和5年10月 第886号 |
【農村の振興】まちからむらから 山形県庄内総合支庁 池田奈菜子 |
幅広い世代(10代未満から80代まで)の住民が参加して集落を探索するワークショップにより、集落内の魅力・課題を分析し、集落戦略や棚田など集落・地域保全のための具体的取組も紹介され、次世代へ受け継ぐ取組は全国どの農村地域においても共感・参考となる内容となっている。 |
| 令和5年11月 第887号 |
【技術ノート】 NTCコンサルタンツ㈱ 都築章宏 |
社会的影響が大きく、技術者としてどのような調査を行ったのか、興味深いものであったが、明治用水頭首工おける漏水事故後の原因究明調査手法が写真や図でわかりやすく紹介されており、耐用年数を超えた農業水利施設が増加する中、今後、同様の事故を発生させないため、漏水発生のメカニズム解明や機能保全調査にも活用されることが期待できる。 |
| 令和5年12月 第888号 |
【技術ノート】 農研機構 農村工学研究部門 相原星哉 |
流域治水の取組を進めるには、洪水調節効果の算定手法の開発が重要であり、本来複雑なシミュレーション等が必要な洪水調節効果について、簡易な手法により図などを用いて効果算定がわかりやすく紹介され、概算でピークカット率を簡単に算出できるため、今後の計画策定の活用にも期待できる。 |
※執筆者の所属及び職名は掲載時のものです。